公開日:2025/04/16 /

日本産の輸出品目の一つである醤油。
海外の日本食ブームもあり、順調に輸出量が増えています。
ここでは醤油の輸出方法について解説します。
醤油の輸出にチャレンジしようとしている方は必見です。
1.はじめに
日本の食文化において、長い歴史をもつ伝統的な発酵食品『醤油』。
大豆・小麦・トウモロコシ・砂糖・グルコース・塩を原料とし、麹菌・乳酸菌・出芽酵母による複雑な発酵過程を経て生成され、昨今の海外における日本食ブームの影響もあって『醤油』が外国人から注目を集めています。
今回は日本の液体調味料の代表格『醤油』の輸出についてご紹介いたします。
2.近年の輸出動向
以下、全ての表とグラフはクリックすると拡大表示されます。
✍醤油の輸出状況(重量と金額)
醤油の輸出は重量、金額ともに右肩上がりです。
海外での醤油需要が増加傾向にあると言えます。
次に2024年の輸出国別の比率を確認します。
✍醤油の輸出国別比率
輸出重量と輸出金額について2位以下はバラつきがありますが、1位は共にアメリカ合衆国です。
2024年時点においてはアメリカ合衆国の醤油需要は大変重要なものだと言えます。
次にアメリカ合衆国への輸出推移を10年に渡って確認します。
✍醤油の輸出状況(アメリカ合衆国)
輸出金額は右肩上がりですが、輸出重量は減少傾向にあります。
2019年の年間平均為替レートが108.05円/ドルで、2024年の年間平均為替レートが150.58円/ドルであったことを考慮すると、アメリカ合衆国内での需要は減少しているものの円安の影響により輸出金額が右肩上がりになったと考えるのが妥当なようです。
この状況ではアメリカ合衆国以外の輸出先も検討した方が良いかもしれません。
そこで2024年の輸出重量上位5カ国について、過去10年間の推移を確認します。
✍醤油の輸出状況(上位5カ国)
アメリカ合衆国は減少傾向、中華人民共和国はほぼ横ばい、英国はわずかに増加傾向という状況の中、ベルギーとオランダは明らかな増加傾向です。
ベルギーとオランダは北海に面して隣接している上に、英国は北海を挟んだ先にあります。広い欧州の中でも割と限られた範囲で醤油の需要が増えているのはとても不思議な現象ですが喜ばしいことだと思います。
欧州において日本食レストランは増えているようなので、ベルギー、オランダ、英国をはじめとした欧州の国々も輸出先として検討するのも良いかもしれません。
3.輸出するにあたっての注意点
✍福島第一原発事故の各国の対応について
福島第一原発事故から12年以上経過し規制は徐々に緩和されつつありますが、下記の国はまだ規制が続いています。
醤油は様々な原材料が使用されています。
その原材料の産地が規制に該当する場合があるので、輸出を検討する際には事前に確認をしておきましょう。
- 中国
- 香港
- マカオ
- ロシア
- 台湾
- 韓国
✍輸入国側規制の確認
相手国により輸入するための規制が異なり、輸入許可や輸入ライセンスが必要となる場合があります。
現地で通関を行うにあたりどのような書類が必要でどのような点に注意すべきか、輸入者に対して事前に確認しておく必要があります。
醤油は加工食品であるため、輸出に際しては製造過程や衛生面、添加物や残留農薬、ラベルなどが相手国側の基準を満たしている必要があります。
■参考:アメリカ向け
アメリカの法制度に対応する関係上、アメリカ側の輸入者と協力してクリアしていくことが重要です。
①米国向けの場合の留意点
米国における輸入加工食品については主として保健福祉省・食品医薬品局(FDA *1)が所管しています。
輸入する加工食品が当該加工食品の衛生基準、商品ラベル、添加物、成分や着色料などがFDAの規準を満たすか確認します。
またバイオテロ法に基づき、 食品関連施設の登録と貨物到着前に貨物の内容をFDAに事前通知(Prior Notice)する必要があります。
事前通知は、FDAのシステム(PNSI *2)を通じて提出する場合は到着予定日の15日前から、
税関国境取締局(CBP *3)のシステム(ABI/ACS *4)を通じて提出する場合は到着予定日の30日前から行うことができます。
事前通知に関するJETROによる解説はこちら
貨物が米国に到着すると、FDAは国内の規準に従ってチェックを行い、適合していれば輸入の許可を税関に通知し、税関は輸入の通関審査を行います。
*1:FDA:Food and Drug Administration(保健福祉省・食品医薬品局)
*2:PNSI:Prior Notice System Interface(事前通知システムインターフェース)
*3:CBP:Customs and Border Protection(税関国境取締局)
*4:ABI/ACS:Automated Broker Interface/Automated Commercial System(自動ブローカーインターフェース/自動商業システム)
②アメリカにおける加工食品の衛生管理・安全性に関する主な規準
- 適正製造規範(GMP)
食品医薬品化粧品法に基づき、FDAは食品の安全性を確保するため食品の製造、包装、保管などの「適正製造規範(Good Manufacturing Practice: GMP)」と呼ばれる衛生基準を設定しています。
GMPを遵守せずに製造、包装された食品は「不良食品」とみなされ、輸入が禁止されます。 - バイオテロ法
2003年12月12日に施行された「バイオテロ法(*5)」により、「食品関連施設の登録」、「輸入時の事前通知」、「記録の保存」、「行政による留置」が義務付けられています。
米国へ輸入される食品を製造/加工、梱包、保管する施設は登録をすると共に、輸入業者は輸入食品が米国に到着する前に、FDAに食品輸入の事前通告を行う必要があります。
未登録の外国の施設から持ち込まれた食品は、通関で留め置かれる可能性があります。
*5:バイオテロ法:公衆の健康安全保障ならびにバイオテロへの準備および対策法(The Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002) - 食品安全強化法
2011年1月に成立した「食品安全強化法(*6)」により、米国の食品輸入業者は、外国供給業者検証プログラム(*7)として、輸入食品に対する食品安全計画の策定と実施が義務付けられています。 また、同法においてバイオテロ法の義務要件の一部が改正され、バイオテロ法に基づく施設登録は、偶数年の10月1日から12月31日の間にオンラインもしくは郵送で登録更新を行う必要があります。
2012年夏以降、米国向けに食品を輸出している米国外の施設に対し、FDAによる査察が実施されています。
*6:食品安全強化法:Food Safety Modernization Act(FSMA)
*7:外国供給業者検証プログラム:Foreign Supplier Verification Program(FSVP) - 食品表示に関する規制
FDAは食品の「基本表示事項」として、以下の項目を英語で記載することを義務付けていますので、注意が必要です。
・主要表示パネル(食品包装の正面中央部分)
・食品名称/識別事項(法規で規定される名称あるいは一般名称)
・内容量・正味重量
・情報パネル(裏面や側面)
・原材料名
・栄養成分表示
・製造業者、包装業者、流通業者のいずれかの名称と住所
・警告および取扱上の注意
・原産国
・アレルギー物質※具体的な原料は、乳、卵、魚(ヒラメ、タラ等)、甲殻類(カニ、ロブスター、エビ等)、ナッツ(アーモンド、クルミ、ピーカン等)、ピーナッツ、小麦および大豆の8種類の食品群
✍経済連携協定(EPA)
下記の国または地域を輸入国とする場合、日本で発行した特定の書類を輸入国側に提出すれば関税の軽減又は免除を受けることが出来ます。
※2025年2月1日時点
| EPA適用国 (協定名) |
基本税率 | EPA税率 | 証明書 ※証明書の説明は欄外に記載 |
|---|---|---|---|
| シンガポール | 無税 | ||
| メキシコ (CPTPP) |
20.0% | 無税 | 自己申告書 |
| マレーシア (日マレーシア) |
10.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| マレーシア (日アセアン) |
10.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| マレーシア (CPTTP) |
10.0% | 無税 | 自己申告書 |
| マレーシア (RCEP) |
10.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 第二種特定原産地証明書 |
| チリ (日チリ) |
6.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| チリ (CPTTP) |
6.0% | 無税 | 自己申告書 |
| タイ (日タイ) |
5.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| タイ (日アセアン) |
5.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| タイ (RCEP) |
5.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 第二種特定原産地証明書 |
| インドネシア (日インドネシア) |
5.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| インドネシア (日アセアン) |
5.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| インドネシア (RCEP) |
5.0% | 3.0% |
第一種特定原産地証明書 |
| ブルネイ (日ブルネイ/日アセアン/CPTPP/RCEP) |
無税 | ||
| フィリピン (日フィリピン) |
15.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| フィリピン (日アセアン) |
15.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| フィリピン (RCEP) |
15.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 第二種特定原産地証明書 |
| スイス (日スイス) |
35CHF/100 kg grs | 無税 | 第一種特定原産地証明書 第二種特定原産地証明書 |
| ラオス (RCEP) |
10.0% | 8.0% | 第一種特定原産地証明書 第二種特定原産地証明書 |
| ベトナム (日ベトナム) |
32.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| ベトナム (日アセアン) |
32.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| ベトナム (CPTPP) |
32.0% | 無税 | 自己申告書 |
| ベトナム (RCEP) |
32.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 第二種特定原産地証明書 |
| インド (日インド) |
30.0% | 無税 | 第一種特定原産地証明書 |
| ペルー (日ペルー)(CPTPP) |
無税 | 無税 | |
| オーストラリア (日豪/CPTPP/RCEP) |
無税 | ||
| モンゴル (日モンゴル) |
5.0% | 0.9% | 第一種特定原産地証明書 |
| EU (日EU) |
7.7% | 無税 | 自己申告書 |
| アメリカ (日米) |
3.0% |
無税 | 自己申告書 |
| カナダ (CPTPP) |
9.5% | 無税 | 自己申告書 |
| イギリス (日英) |
6.0% | 無税 | 自己申告書 |
| ニュージーランド (CPTTP) |
5.0% | 無税 | 自己申告書 |
第一種特定原産地証明書とは
これらのEPAを利⽤するためには、⽇本商⼯会議所から第一種特定原産地証明書を取得する必要があります。
第二種特定原産地証明書とは
自己申告書とは
なお、《原産地申告書》の作成者が誰であるかに関わらず、輸出先国・地域の税関当局が、産品が原産品であることを確認するために追加で情報や資料を要求してくる可能性があります。
4.輸出に必要な書類
輸出通関に必要な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 書類作成者等 |
|---|---|
| インボイス※ | 輸出者が作成。 インコタームズ、商品名、学名、個数、単価、金額、合計金額を記載。 |
| パッキングリスト※ | 輸出者が作成。 商品名、材質、個数、重量を記載。 |
| 経済連携協定書類 《第一種特定原産地証明書》 《第二種特定原産地証明書》 《自己申告書》 など |
輸出者や商工会議所が発行。 ※輸出先国・地域が協定適用国の場合に必要。 |
| 福島第一原発事故対応書類 《放射性物質検査証明書》 《産地証明書》 《輸出事業者証明》 など |
地方農政局や放射能検査機関で発行。 ※輸出先国・地域が福島第一原発事故規制対象国の場合に必要。 |
※インボイスとパッキングリストは情報が重複する部分が多いので「INVOICE&PACKING LIST」として内容を1枚に集約しても構いません。
5.輸出通関「税関申告」
✍輸出HSコード ※2024年1月
■醤油:2103.10-000
✍税関へ申告
インボイス・パッキングリストをもとに《輸出申告書》を作成します。
《輸出申告書》にインボイス、パッキングリスト等必要書類を添付して申告します。
審査が完了し、問題が無ければ《輸出申告許可書》が発行されます。
※《輸出許可書》は輸出者がインボイス等の輸出書類とともに5年間保存する必要があります。
▶▶▶通関申告はアクセス・ジャパンにお任せください◀◀◀
お見積りは こちら から
6.輸送コスト計算の注意点
物流費用というのは「100kgの鉄」と「100kgの綿」では「100kgの綿」を運ぶ方がコストが掛かります。
綿のほうが輸送スペースを必要とするからです。
物流コストは、実際の重量(Actual Weight)と容積重量(Volume Weight)を比較して、数値が大きい方が採用されます。
海上コンテナはコストがコンテナ単位なので割愛します。
海上輸送 LCL(混載)と航空輸送に絞って解説します。
✍海上輸送 LCL(混載)の場合
LCLとはコンテナを満載にする物量がない複数の荷主を集めてコンテナを仕立てる方法です。
コスト計算の単位は実重量と容積重量の大きい数値が基礎となります。
実重量は、「商品そのものの重さに梱包資材を加えた重さ」です。
つぎに容積重量ですが、注意が必要です。
LCLの場合、容積1m3(1x1x1m)の商品は1,000kg扱いとする、
と定められています。
1,500kgの商品が容積1m3の場合、計算の基礎は1,500kgとなります。
100kgの商品が容積2m3の場合、計算の基礎は2,000kgになるので注意が必要です。
※なお、LCLの最小重量は1m3(1mx1mx1m)、1,000kgです。
容積0.5m3の場合や重量500kgの場合、容積1m3、重量1,000kgとみなされるので注意が必要です。
✍航空輸送の場合
実重量はLCLと同様、商品そのものの重量です。
問題は容積重量です。
航空輸送の場合の容積重量は計算式があります。
航空輸送の容積重量=縦cm x 横cm x 高さcm ÷ 6,000
となっています。
例えば、容積1m3で100kgの商品において、容積重量は
1m3(100cm x 100cm x 100cm)÷ 6,000=166.67kg
となります。
この場合、運賃計算の基礎は100kgではなく166.67kgになります。
※国際宅急便(DHL、Fedex、UPSなど)は独自の計算方式になっているので、注意しましょう。
7.まとめ
世界的な日本食ブームに加え、グルテンフリーやオーガニック食品の需要の高まりにより注目されている『醤油』。
今後更に需要が高まることが予想されている『醤油』の輸出について弊社がお手伝いさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
また、進め方に不安や不明点がある方は国際物流コンサルティングサービスをご検討ください。
アクセス・ジャパンではその不安を一緒に解消し、輸入貿易を成功に導くノウハウをお伝えします。
まずは無料のヒアリングから行いますのでお気軽にご相談ください。
コンサルティングの詳細は こちら
お問い合わせはこちら
些細なことでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。
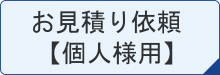
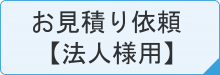
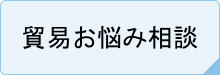
-335x412.png)
-745x455.png)
_R-745x594.png)
_R-745x594.png)
-335x412.png)
-745x455.png)
-335x198.png)
-745x455.png)